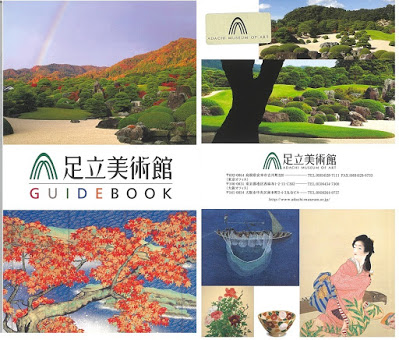「鷺の湯」と呼ばれる湯郷温泉。
貞観2年(860)、作州行脚をしていた慈覚大師円仁が薬師如来の化身に導かれ、白鷺が湯浴びをしている温泉を発見したと伝えられています。
泉質はナトリウム、カルシウム塩化物泉で、消化器病、神経痛、リュウマチ、貧血症、婦人病、皮膚病などに効果があり、美肌づくりの湯としても女性に人気があるそうです(湯郷温泉旅館協同組合の湯郷温泉ナビより)。
足湯の「ふれあいの湯」の前に塩湯社があり、おまつりされている岩から流れ出る湯が源泉のようです。
塩湯社の碑には「古人は体を温め傷を癒やしてくれる温泉に畏敬をして湯の神様を祀り、塩湯社と称した。やがて鷺温泉の名は広まり、奈良時代には貢物として湯を都に運んだ」ということが書かれていました。
少し離れた小高い位置に長興寺と湯神社があります。
長興寺は円仁法師によって創建されたと伝えられています。元弘2年(1332)に後醍醐天皇が隠岐へ配流されたときは、湯郷温泉に立ち寄り長興寺に滞在されたと考えられているそうです。
長興寺のお隣には湯神社があります。
ご祭神は大己貴命、少彦名命、譽田別尊、大山祇命です。
土用の丑の日に温泉につかると、1年間、無病息災、元気に暮らせるという言い伝えがあり、丑湯祭りでは湯神社に源泉が奉納されます。
湯郷温泉では他にもたのしい工夫がされています。
ゆ~らぎ橋
鷺湯公園の梅干し
さんぶ太郎
温泉街から少し離れたところにからくり時計があります。高さは8m、幅4mという大きな時計です。からくり時計の中から美作、湯郷に関係がある慈覚大師円仁、宮本武蔵、さんぶ太郎が出てきます。
さんぶ太郎については次の説明がありました。
岡山県を代表する伝説に、巨人伝説『さんぶ太郎』があります。
湯郷温泉からくり時計の説明板より
昔、豪族・真兼が、地元の菩提寺(岡山県奈義町)に参拝したとき、美しい女子と出会い、恋仲となった二人は契りを結びました。
そして、二人の間には 男の子が生まれ、『太郎』と名付けられました。
真兼は、妻から産室も授乳も見てはならぬと言われていましたが、ある日約束を破り部屋の中を覗き見ると、そこに居たのは妻ではなく蛇体でした。
正体を知られた妻は、『太郎』を残し真兼の元を去りました。
その後、『太郎』は人並みはずれた巨人に成長し、京都へ三歩で行ったと伝えられています。
これが『さんぶ太郎(三歩太 郎、三穂太郎)』と呼ばれるようになった由縁です。
からくり時計を突き破って大きなさんぶ太郎が登場します。
さんぶ太郎は箸で何かを掴んでいます。それは湯郷に伝わる伝説に関係がありました。
ある日、『太郎』が那岐山に腰かけて飯を食べていると、飯の中に二つの石が入っていました。『太郎』はその石をつまみ出し足元に重ねて積みました。その重ねられた(積まれた)小石は、重岩【かさねいわ(積岩/つみいわ)】と呼ばれ、湯郷温泉の西の端にあります。
湯郷温泉からくり時計の説明板より
鷺湯公園から少しいったところに重岩がありました。大きな石です。
こんなに大きな石を積み重ねることができるのはさんぶ太郎だけです。
からくり時計がおもしろくて、さんぶ太郎の印象が強烈に残ってしまいました。
でも、温泉も旅館の食事もよかった。
湯郷温泉。また来てみたいなと思えるところでした。