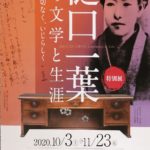別府の住吉神社にお参りしました。この神社も松で有名です。

御祭神は底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、表筒男命(うわつつのおのみこと)と息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)です。
住吉神社なので底筒男命、中筒男命、表筒男命の神様は必ずおられます。この三神は住吉三神と言われるそうです。
イザナギノミコトが黄泉の国から戻ったときに、ケガレを落とそうとミソギをおこないました。
このとき、瀬の深いところで底筒男命、真ん中ぐらいのところで中筒男命、水面で表筒男命が生まれ出たとされています。
息長足姫命は神功皇后で、住吉神社に深い関係があります。


境内には「手枕(たまくら)の松」という有名な松があります。

松が横に傾き、腕枕のように見えることから別府出身の俳人滝瓢水(たきひょうすい)によって手枕の松と名付けられました。
※ 滝瓢水
貞享元2年(1684)〜宝暦12年(1762) 江戸時代中期の俳人。
播磨国加古郡別府村の生まれ。実家は富裕な船問屋であったが、滝瓢水の放蕩で没落した。

初代の松は大正末期に枯れ、今生えている松は3代目です。
確かに、すごく横に傾いています。
尾上神社の「片枝の松」と似ている生え方です。
別府住吉神社は播州松巡りの東端に位置します。
松巡りは東から
別府住吉神社「手枕の松」
浜宮天神社「菅公のお手植の加古の松」
尾上神社「尾上の松」、「片枝の松」
高砂神社「高砂相生の松」
曽根天満宮「霊松曽根の松」
と続きます。