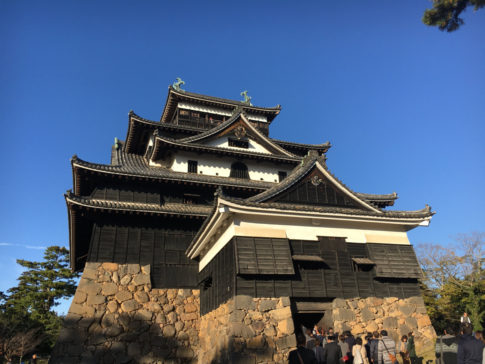岡山市にある最上稲荷におまいりしました。
最上稲荷は神社ではなく、正式名称が「最上稲荷山妙教寺」という日蓮宗の寺院です。
由緒は次のように伝えられています。
天平勝宝4年(752)、報恩大師が孝謙天皇の病気平癒のため、龍王山中腹の八畳岩の岩窟に籠もり、祈願したところ21日目の早暁に最上位経王大菩薩(最上尊)を感得。そのお姿を自ら刻み祈願を続けると、天皇は快癒された。
延暦4年(785)、桓武天皇のご病気も、大師の祈願により快癒。これを喜ばれた天皇の命により、現在の地に「龍王山神宮寺」が建立された。
羽柴秀吉による備中高松城水攻めの際、戦火によって堂宇を焼失。本尊の「最上位経王大菩薩」のみが八畳岩の下に移され難を免れた。
慶長6年(1601)、足守の領主となった花房公が日円聖人を招き、寺名を「稲荷山妙教寺」と改めて、今日の興隆の礎を築いた。
また、明治の廃仏毀釈の際、神仏習合が許されました。
大鳥居
仁王門
さらに裏側は銀のお稲荷様でした。
本殿
本殿は巨大です。
開山千二百年記念事業として計画され、昭和54年(1979)に完成した建物でした。年間約300万人もの参詣者をお迎えしている建物です。プロ野球の球場なんかよりずっと多い人数です。
お香の煙がもうもうとしています。
縁の末社
縁切りと縁結びができる縁の末社です。両方合わせて行うのが最上稲荷の特徴とになっています。
「 縁むすび と 縁きり は相反する事柄ですが、良い縁を結ぶためには、まず今あるしがらみを一度きれいに絶ち切ることが大切」
という教えです。
縁切りはちょっと・・・と思いますが、「縁きりとは相手に不幸をもたらすものではありません。たとえ自分にとって望ましくない縁でも、自分を成長させてくれた縁として感謝し、一区切りを付ける機会と捉えてみてはいかがでしょうか」とあります。すごくポジティブです。
最上位 離別天王
ご威徳:縁切、悪縁退散
人の縁に限らず、病気・酒・煙草・賭け事等々のあらゆる悪縁を断って下さる天王として古くから信仰されている。
最上位 縁引天王
ご威徳:縁継、良縁成就、諸芸上達。
男女の縁に限らず、仕事・学業・夢等々のあらゆる福縁を結んで下さる天王として古くから信仰されている。
旧本殿・霊応殿
寛保元年(1741)年に再建された建物で、当山最古の木造建築物。
三面大黒堂(金運堂)
尊像は最上三神の三面大黒天で、中央は大黒天、正面左は毘沙門天、正面右は弁財天です。
「お堂を囲む水盤の水は当山報恩大師以来一千二百年の歴史がある巌開明王池から移した霊石が納めてられていて、霊験はあらたかで、この清水に浸したものを清める功徳がある」ということです。
最上尊降臨の霊地・八畳岩
八畳岩
由緒にあるように、約1300年前、報恩大師が孝謙天皇の病気平癒を祈願し、最上尊が降臨したという八畳岩。畳が八畳敷ける広さがあるためこの名が付いたといわれています。
平べったい大きな岩です。
報恩大師が籠ったという岩窟は狭いです。報恩大師は小柄な人だったかもしれません。
巌開明王
報恩大師がご修行の際に端座された岩(巌)の一つが割れ、清水がわき出したという伝承から「巌開明王」と名付けられました。
奥の院 一乗寺
八畳岩からさらに登っていくと、奥の院一乗寺です。
途中、数カ所の鳥居があり、参道の両側は石造物がいっぱい立ち並んでおり、神秘的でもあります。
最上稲荷は、黄金の仁王様がおられる山門、巨大な本殿、縁の末社などの派手派手しさと、龍王山上の八畳岩、奥の院一乗寺では強い信仰心を感じられる神秘的なパワースポットを併せ持つ、楽しい寺でした。
人気があるのもうなずけました。