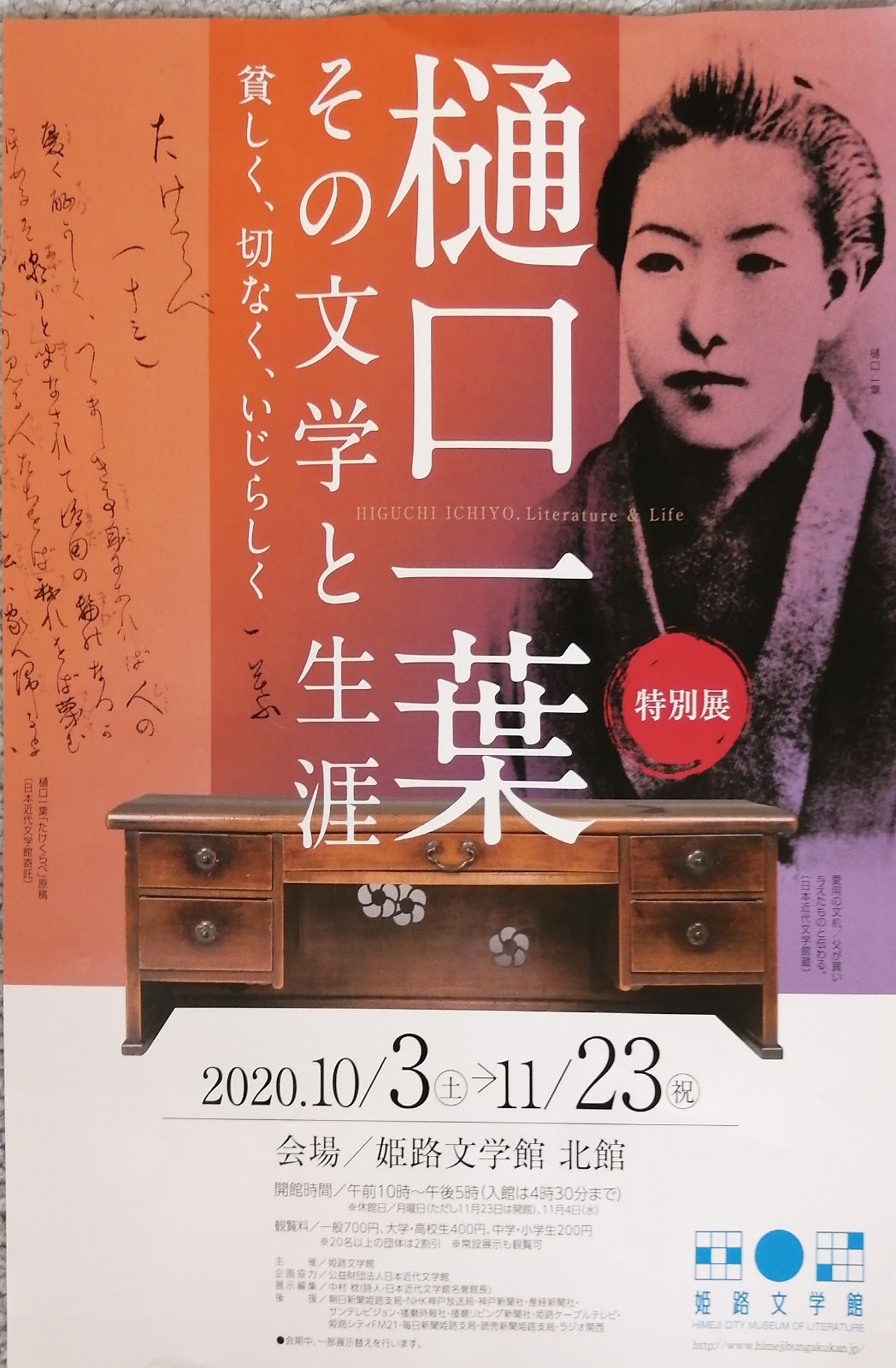姫路藩家老
河合寸翁の事業の一つに東山焼(とうざんやき)があります。
東山焼は河合寸翁の時代、姫路市東山(ひがしやま)で始まりました。
その後、姫路藩御用窯に指定され、窯は男山山麓に移り、京焼、伊万里焼の技術を取り入れた高級な磁器が作られました。次期藩主酒井忠学と徳川家斉の娘喜代姫との婚約・結婚のために使われたと考えられています。
東山焼は喜代姫と結婚した天保3(1832)年頃が最盛期で、河合寸翁が死去(天保12年/1841)したあと衰退していきました。
現在の東山には窯の跡の碑があるだけで、何も残っていません。

看板には次のように説明が記されています。
東山焼は、江戸時代の後期に東山で始まった焼き物であります。
当時東山村の圧屋だった八代目橋詰山三郎の弟、藤作が興禅寺の南東斜面の山腹に登り窯と作業場を築き、総取締役になり、瓦職人だった池田屋弥七が陶工となって、茶碗・鉢・皿・花瓶・壷などを焼いて文政五年(一八ニ二)から製造が始まりました。
その後、東山焼は姫路藩家老河合寸翁の推奨によって姫路藩御用窯に指定され、天保二年(一八三ー)頃、姫路市山野井の男山山麓に窯を移されました。
男山に移ってからの東山焼は、青磁の逸品や京焼風のすぐれた磁器を生産し、将軍家にも献上されるなど、東山焼の名は大いに高まりました。
しかし、河合寸翁が天保一二年(一八四一)に没すると男山窯は一定の役目を終えたこともあって、安政年間(一八五四〜六〇)に藩の御用を解かれました。その後、民窯としてしばらく存続しましたが、明治に入り、製造されなくなりました。
なお、橋詰藤作および池田屋弥七の墓碑は海久寺にあります。
池田屋弥七作の拍犬は、昭和五八年に姫路市立美術館に寄託されています。平成二三年一月 姫路市教育委員会
姫路市書写の里・美術工芸館に展示されている東山焼

写真で見る東山焼は青色がきれいで美しい。
実物をたくさん見てみたい。
実物をたくさん見てみたい。