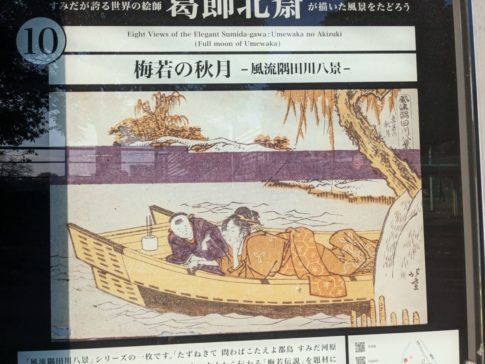西郷隆盛像、清水観音堂、不忍池弁天堂から五条天神社、上野大仏、おばけ灯籠を巡って、次は上野東照宮です。
元和2年(1616)4月17日、徳川家康が亡くなります。
家康公は「東照大権現」という名でおまつりされました。
その東照大権現をまつるのが東照宮です。
その年のうちに久能山に、翌年の元和3年には日光に東照宮が建てられました。
浅草寺、増上寺、江戸城内の紅葉山にも東照宮が建てられ、寛永4年(1627)には藤堂高虎が上野に東照宮を私費で建てました(浅草寺の東照宮が寛永19年に焼失)。
それから約20年後、徳川家光公は藤堂高虎が建てた東照宮を撤去して、新たに東照宮を建てました。この東照宮が今に残る上野東照宮です。
上野東照宮の落慶式が行われたのは慶安4年(1651)4月17日。家康公の命日でした。
東照宮の看板にある「1627年創建、1651年造営」とは、藤堂高虎の最初の東照宮が建てられたのが1627年で、家光公が東照宮を建て直したのが1651年ということでした。
神社の入口に石鳥居があります。高さ5メートルの大きなものです。
寛永10年(1633)、家康公の命日である4月17日に上州厩橋城主・酒井忠世によって奉納されました。
鳥居が造られたのは家光公の東照宮ではなく、藤堂高虎の東照宮の頃ですね。
石は備前(岡山)から運ばれたものです。よく、そんな遠くから運んできたものです。
この鳥居は一時期、幕府の命令で解体されて地中に埋められ、八代将軍・徳川吉宗の時代に掘り起こされたという歴史があります。地中に埋められた理由ははっきりとはわからないそうです。
こんな大きく重そうなものを人力でバラしたり組み立てたりできるのですね。
水舎門をくぐると唐門まで参道が続きます。
参道の途中に寛永寺五重塔があります。
最初の五重塔は寛永8年(1631)老中・土井利勝の寄進によって建てられました。しかし、8年後の寛永16年(1639)に焼失。
すると、土井利勝が再び寄進を申し出て、その年のうちに五重塔が完成。これが現在の五重塔です。わずか一年で完成するとは。ものすごいスピードです。
参道の突き当たりは唐門。金ピカでゴージャスです。
唐門の前には諸国の大名が奉納した銅燈籠、御三家灯籠が並びます。
御三家灯籠が奉納されたのは慶安4年(1651)4月17日。家光が建てた上野東照宮の落慶式の日でした。
拝観料を払って東照宮の中に入ります。
大楠を過ぎて少し進むと朱色の鳥居があります。「栄誉権現」と言うそうです。
「四国八百八狸の総帥で、奉献された大奥で暴れ追放後大名旗本諸家を潰し、大正年間本宮に奉献された悪行狸。他を抜く(たぬき)強運開祖として信仰が厚い」という説明があります。
悪いたぬきのようですが、勝負には強そう。
神田の柳森神社にも「他を抜いて(たぬき)玉の輿に乗った桂昌院の幸運にあやかりたい」ということでたぬきがおまつりされています。
たぬきには勝負に勝つという語呂合わせがあるのですね。
社殿を取り囲む透塀は向こう側が見えるのでこの名がつけられています。精巧な細工が施されており2024年の干支のうさぎがいました
社殿は別名金色殿と呼ばれています。その名の通り金ピカです。侘び寂びなんかまったくありません。日光の東照宮も金ぴかで派手派手しいですが、こうすると家康公が喜んでくれると思ったのかな。
ケチな気持ちがあったら、こんなことはできませんね。
社殿側から見る唐門もすごいです。
金色殿、唐門、透塀の屋根は銅瓦葺ということで青緑色をしていました。慶安4年(1651)4月17日の落慶式では金色に輝いていたと思います。
建物も屋根も全体が光っているところを見たかった。
それにしても、よくぞこんな建物を造ってくれました。今まで残ってきたことに、守ってきてくれたことに感謝です。