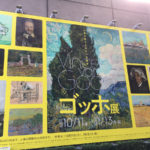松原八幡神社で行われる秋祭りは「灘のけんか祭り」といって兵庫県の重要無形民俗文化財に指定されています。
御祭神は、品陀和気命(ほんだわけのみこと、応神天皇)、息長足姫命(おきながたらしひめのみこと、神功皇后)、比咩大神(ひめおおかみ)。
創建は天平宝字7年(763)とされています。古い歴史を持つ神社です。
楼門は延宝7年(1679)12月の建立で、江戸時代中期の播磨の代表的な楼門ということです。
境内に倶釣社というお社があり、神社創建のエピソードに出てくる久津里をお祀りしています。
「姫路の神社」という兵庫県神社庁姫路支部編著によると神社の創建は次のように書かれていました。

天平宝字七年(763)豊前宇佐より白雲が東にたなびき、松原沖の海底に毎夜光り輝くものがあった。国司が妻鹿の漁人、倶釣(久津里)に命じて網を入れさせたところ「宇佐第二垂迹八幡大菩薩」の文字のある紫檀の霊木があがったので、妻鹿川の下流の大岩の上に安置してお祀りした。
「姫路の神社」より
このことが当時の朝廷に聞こえ、勅使が下向し妻鹿の北東の山頂(お旅山)に仮殿を造り御神体をお遷しした。ある夜、国司は神のお告げを夢に見た。それは「我が永久に鎮座しようと思う所は今は、海原であるが、そこを一夜にして白浜とし、栗が生じるように数千の松を生やすから、そこに移して祀れ」というものであった。そこで国司は諸国の工人を集め、豊前の宇佐宮に倣って立派な社殿を造営し、御神体を松原の地にお遷しした。
神社はもともと現在地にあったと思っていたのですが、2回お遷りがあったのですね。
その後の歴史は以下のようです。
- 平安時代に松原荘が石清水八幡宮の社領(荘園)となる。
松原八幡宮はその荘園鎮守となる。
その頃に松原八幡宮の放生会が始まったものと考えられる。
これが今の灘のけんか祭りのルーツのようです。 - 鎌倉時代には八幡菩薩垂迹の地として崇敬を集め、一遍上人の参詣も知られる。
- 南北朝時代の「峯相記」に社頭繁盛し、神事祭礼厳重と記される。
- 天正五年(1577)織田信長の命を受けて中国平定のため播磨に入った羽柴秀吉が播磨の諸城を攻めたとき、松原八幡神社は秀吉方に味方し、三木城の別所長治と対立。長治を援助する毛利輝元の軍船が来襲して兵火にみまわれた。
- 天正九年(1581) 秀吉は松原八幡神社に城南芝原(現在の豊沢町)へ移ることを命じたが、松原の地は由緒ある土地であることを理由に移転を拒んだ。秀吉は怒りをかい、社領が 60 石に減じられた(飾磨郡誌)。
- このとき、黒田官兵衛の懇願により松原八幡神社は移転せずにすみ、現在地で存続できたと伝えられている。
黒田二十四騎の一人・井上九郎右衛門之房は福岡藩知行割の資料に「播磨飾東郡松原郷桂村人」とあり、当地松原の出身とされる。 - 江戸時代は 60 石が所領になる。
しかし、地元(氏子)は農業だけではなく商売で裕福な地だったようで、祭りがだんだんと神様に仕える祭りから氏子が楽しむ祭りに変わっていった。 - 明治になると、亀山雲平氏が松原八幡神社の祠官となられる。雲平氏は今の白浜小学校の地に講堂、寄宿舎を建て「観海講堂」と命名。播磨一円の子弟の教育にあたりました。
境内に亀山雲平先生遺蹟の碑があります。観海講堂の碑が白浜小学校に建てられています。
境内に樹齢500年という大イチョウが植わっています。松原八幡神社の歴史、祭りをずっと見守っています。