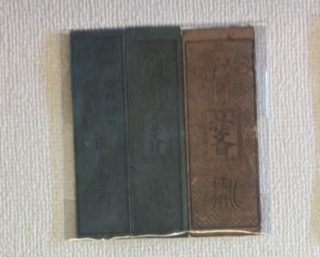姫路藩家老の河合寸翁は借金に苦しむ姫路藩を救い、姫路の基礎を作りました。
文化五年(1808)、42歳で姫路藩の諸方勝手掛となり、藩政改革に挑みました。
73万両の借金を10年ほどで返済しています(73万両は藩の実収入の7倍以上の金額)。
藩政改革にあたって、基本とした考えは「君と臣は一体のもの」という考えでした。
※諸方勝手掛:すべての収支を見る役職
河合寸翁の事績
河合寸翁は借金を返済し、さらに姫路を豊かにするために、いろいろな事業を行っています。そして、それは経済のことだけではなく、教育、庶民の暮らしの厚生と幅広いものでした。
- 木綿(姫路木綿・玉川晒)の藩専売制、江戸直売
- 藩札・木綿切手の発行
- 新田、塩田の開発
- 飾磨、木場、高砂の港を整備
- 塩や藍などの殖産興業
- 皮革、鋳物、鉄製品、染物の専売制
- かりんとう、玉椿
- 朝鮮人参
- 東山焼
- 教育(好古堂、仁寿山黌、申義堂)
- 固寧倉
財政
木綿などを専売制にし、藩が商品を買い上げ、取りまとめて売るシステムで大きな利益を得ました。
木綿は大阪商人を介さず、江戸で直売しました。姫路の木綿は姫玉、玉川晒と呼ばれて大人気と商品となりました。
金融政策にも気を配り、御国用積銀の制度で領民から出資を募り、債務返済に使うとともに、切手会所で藩札(木綿切手)を発行しています。木綿切手は切手会所でいつでも金、銀、銅銭に替えることができ、姫路藩の藩札は信用され、江戸でもお金として流通したということです。
銀行業を興したような感じです。
教育
藩校・好古堂の改革、私学校・仁寿山黌、郷校・申義堂を設立を行いました。
好古堂
酒井家が前橋にいたときから好古堂は開校していました。
寸翁の時代には好古堂の在校者が少なくなっていましたが、場所を今の好古園のところに移転するとともに規模を拡大しています。
好古堂は藩士子弟に教育を行い、朱子学以外の学問は禁じられていました。
仁寿山黌
仁寿山黌は河合寸翁が開校した私立学校です。武士も庶民も学ぶことができ、朱子学だけではなく国学、蘭学、医学を学べました。
頼山陽などの一流の学者が来校し講義をおこなっています。
寸翁は厳格な好古堂に対し、開放的な学校を目指したと考えられます。
結果として、仁寿山黌は勤王思想を持つ人材を多く生みました。
これが藩の上層部には問題視され、寸翁死去後、仁寿山黌は医学寮を残し廃校となり、好古堂に吸収されました。
社会厚生
飾西郡の大庄屋 衣笠氏長の建議を取り入れ、固寧倉を創設した。 固寧倉では飢餓、災害に備え米、麦、籾を貯蔵しました。天保の飢饉(1836、1837年)でも姫路では被害がほとんど出ませんでした。
また、災害のないときにも安い利息で米、麦を貸し付けることによって、農民の生活が安定化しました。
姫路藩内に288箇所の固寧倉があったということです。
河合寸翁の名前の変遷
寸翁という名は隠居してからつけた名前です。
幼名 猪之吉
16歳 隼之助
54歳 道臣 前藩主 酒井忠道の一字をもらう。
69歳 寸翁 隠居後に寸翁と名乗る。
仕えた藩主
寸翁は4代の藩主に仕えました。
- 酒井忠以
酒井姫路藩第2代藩主。
芸術に才能があったお殿様です。弟は江戸琳派の画家 酒井抱一。 - 酒井忠道
寸翁に諸方勝手掛を命じ、藩政改革を進めたました。
寛政二年(1790) 12歳の時に父の死により家督を継ぎます。
文化五年(1808)に寸翁に諸方勝手掛を命じたときは30歳でした。 - 酒井忠実
寸翁の藩政改革を支援し、多くの改革を実現させました。
仁寿山の地を寸翁に与えました。 - 酒井忠学
徳川家斉の娘 喜代姫と結婚しました。景福寺に喜代姫の墓があります。

河合寸翁の思想
寸翁は山崎闇斎の学系に属するとされています。
その交友関係から寸翁は勤王思想を持っていたと考えられます。
寸翁の歌
さしのぼる 日の本なれば 我国は よろづの国にも まさる春かな
甲斐なくも 我がものがほに しぬるかな 君にゆるせし 命なりしを(辞世の歌)
寸翁の思想は仁寿山黌での教育に影響したと想像できます。
河合寸翁に関わる人々
川合勘解由定恒
寸翁の祖父。
酒井家家老。酒井家の前橋から姫路へ所替えにあたり総指揮をとった。
寛延二年(1749)大雨により船場川が決壊し、姫路城下は大洪水となり、337人が死亡した。そのとき、独断で避難民を城内に収容し、被災者に備蓄米を与えた。
寛延四年(1751)本多光彬、犬塚又内を自邸で殺害し、自害した。
河合家は御家断絶となる。
川合宗見
定恒の死後、26年後の安永七年(1778)家老に復帰した。
河合屏山
松下源太左衛門高知の次男。寸翁の養子となり河合家を継ぐ。
姫路の尊皇攘夷派の中心的存在。甲子の獄で謹慎処分を受け、江戸で監禁される。
明治維新で家老に復帰。佐幕派を処罰する(戊辰の獄)。
日本で最初に版籍奉還を建議する。

河合宗元惣兵衛
河合寸翁家の分家の家系。
姫路の尊皇攘夷派の中心的存在。甲子の獄で自殺刑となる。
墓は善導寺にあります。
河合寸翁の年表
寛延四年 1751 祖父 定恒切腹。
明和四年 1767 河合寸翁誕生。幼名は猪之吉。
安永六年 1777 11歳 藩主 忠以に仕え、書画などの手ほどきを受ける。 寸翁は多趣味の人でもあったようだ。茶は宗匠の格、書画骨董の鑑定にすぐれ、算数ができ、囲碁は初段の腕前だったらしい。
天明二年 1782 16歳 名を隼之助に改める。
天明七年 1787 21歳 父 宗見死去。家督を継ぎ、家老職につく。
寛政三年 1791 25歳 結婚
寛政五年 1793 27歳 出府。3ヶ月後、姫路に帰る。
寛政七年 1795 29歳 母死去
寛政九年 1797 31歳 出府。6ヶ月後、姫路に帰る。
寛政十二年 1800 34歳 祖父 定恒の五十回忌。
文化二年 1805 39歳 松下源太左衛門高知の次男 良翰(河合屏山)を養子にもらう。
文化五年 1808 42歳 諸方勝手掛を拝命し、財政改革を任される。
文化六年 1809 43歳 固寧倉の創設の儀を提出。固寧倉を設立を開始する。
文化七年 1810 44歳 木綿の江戸直売の届出書を提出する。姓を川合から河合に改名する。
文化八年 1811 45歳 高砂港を整備する。施主は工楽松右衛門。
文化九年 1812 46歳 藩校 好古堂の改革に着手。申義堂を創立する。
文化十年 1813 47歳 御国用積銀の制度を始める。
文化十三年 1816 50歳 藩校 好古堂が完成。
文政三年 1820 54歳 御切手会所を作り、藩札を発行する。藩主 から道臣の名を賜る。
文政四年 1821 55歳 仁寿山黌の建設を始める。御国産会所を御切手会所に併設。
文政五年 1822 56歳 将軍家斉の娘喜代姫と藩主・忠学が婚約。医学寮ができ、仁寿山黌が完成。
文政六年 1823 57歳 木綿の江戸直売議定書成立。
文政七年 1824 58歳 頼山陽が仁寿山黌に来校。
文政十年 1827 61歳 第一回目の隠居願いを出すが、受理されず。
天保元年 1830 64歳 的形新開塩田が完成。人参役所設置。
天保三年 1832 66歳 喜代姫と藩主・忠学が結婚する。
天保六年 1835 69歳 隠居氏、家督を良翰に譲る。寸翁と改名。
天保十一年 1840 74歳 祖父 定恒の遺骨を仁寿山梅ヶ岡墓所に改葬する。
天保十二年 1841 75歳 死去。仁寿山梅ヶ岡墓所に眠る。
天保十三年 1842 仁寿山黌が医学寮を残して廃校になる。
元治元年 1864 甲子の獄
明治元年 1868 戊辰の獄
明治九年 1876 河合屏山 死去
以下の資料を参考にさせていただきました。
姫路市教育委員会 天下の名家老 河合寸翁
寺林峻著 姫路城 凍って寒からず
熊田かよこ著 河合寸翁
糸田恒雄著 河合寸翁の業績と姫路藩の勤王思想